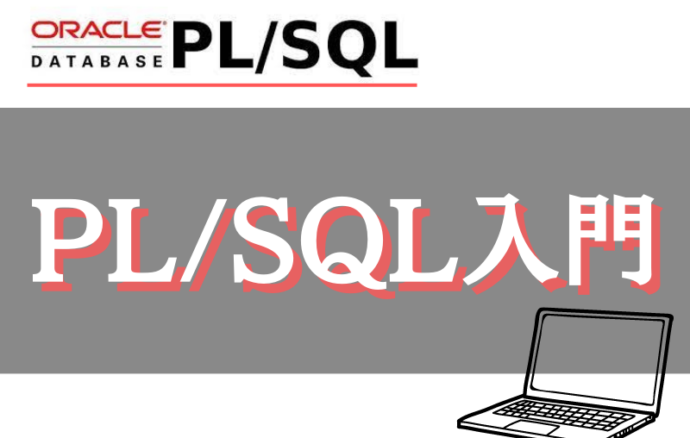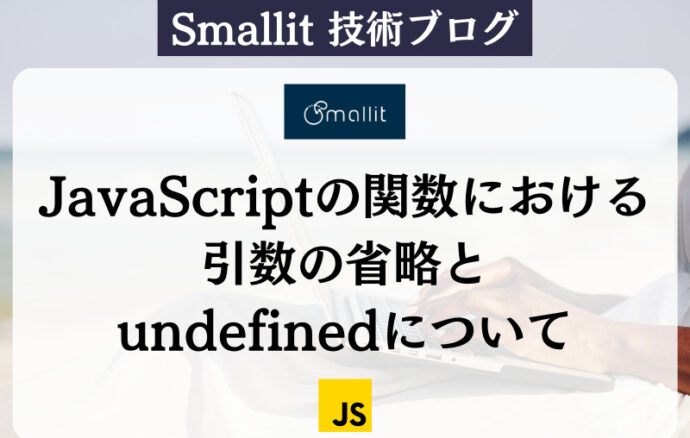- 開発技術
単体テスト・品質を保ち作業効率を上げる
- 生産性向上
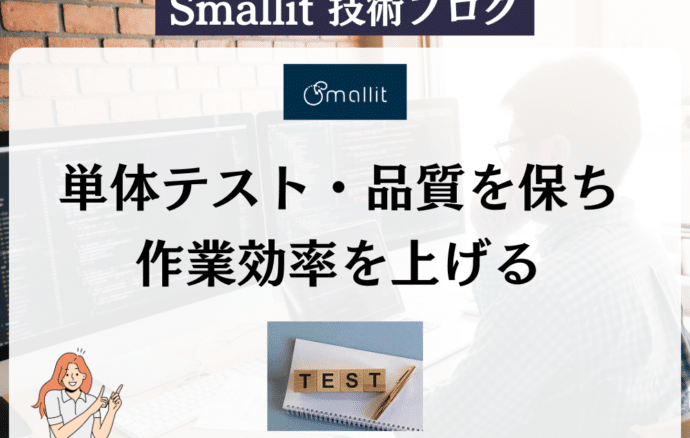
目次
【エンジニア募集中】フルリモート可◎、売上/従業員数9年連続UP、平均残業8時間、有給取得率90%、年休124日以上 etc. 詳細はこちらから>
1:単体テストの目的
2:単体テストの重要事項
3:作業効率を上げるための実践ポイント
4:避けたいアンチパターン
5:まとめ
単体テストの目的
単体テストは、アプリケーション内の最小単位(メソッドやクラス)を検証するテストです。
大きく分けると主に以下のような目的があります
・ロジックの正当性の検証(仕様通りか)
・リグレッション防止(既存機能の破壊を防ぐ)
・リファクタリングの安心材料
・ドキュメント代わりになる
単体テストの重要事項
1.自己完結
・依存先(DB、API、ファイルシステム)に依存しない事
・モック/スタブを活用して外部影響を排除
2.意図を明確に
・入力、処理、期待結果を明示的に記述
・テスト名や関数名も「~すべき」「~であること」のように読みやすく
網羅性とメンテ性のバランスをとる
・完全網羅できることが理想ですが、現実的には重要ロジック・分岐に焦点を絞る
・コーナーケース(null、空文字、上限/下限)なども忘れずに行う
作業効率を上げるための実践ポイント
1.テスト対象の設計を意識する(テストしやすいコードを書く)
・単一責任の関数に分ける(SRP原則)
・依存性注入(DI)を活用してテストしやすい構造に
・非同期・副作用のある処理は分離する
2.テストコードをDRYに保つ
・テストデータの共通化(Factory、Builderパターン)
・テストセットアップの整理([TestInitialize]、SetUp())
3.モックを賢く使う
・MoqやNSubstituteを使って、依存するサービスを仮装
・過度なモック地獄に陥らないように注意(テスト対象が小さく分かれていることが前提)
4.カバレッジより「意図を持ったテスト」
・カバレッジ100%を盲目的に目指すのではなく、失敗しそうな箇所・重要な分岐を優先
5.CIで自動実行+失敗時は即通知
・GitHub Actions / Azure DevOps / GitLab CIなどで、テストは毎回自動実行
・失敗時はSlackやTeamsに通知すれば早期対処が可能に
避けたいアンチパターン
| アンチパターン | 解説 |
| テストが外部サービスに依存 | テストが不安定になりCIが失敗しがちに |
| 複数条件を1つのテストで | テスト失敗時にどの条件が原因か特定しづらい |
| テストが長すぎる | 保守性が下がり、新しい開発者が理解できなくなる |
| 無意味なアサート | Assert.AreEqual(true, true); などは意味がない |
| テストデータがハードコードされている | 入力値変更が面倒、流用が効かない |
まとめ
・単体テストは「時間の無駄」ではなく、「将来のバグ対応コストを抑える投資」
・最初は面倒でも、書けば書くほど開発スピードと安心感が増してきます
・特にチーム開発では、壊したらすぐにわかることや、変更に強いことが大きな価値になります
【エンジニア募集中】フルリモートも◎(リモート率85.7%)、平均残業8時間、年休124日以上、有給取得率90% etc. 詳細はこちらから>